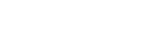「ボスの屋敷は街外れの森にある。迷うと帰ってこれなくなるから、はぐれるんじゃねえぞ」
イングウェイは古ぼけた地図を眺めながら、深紅の森を歩いていく。あたりには濃い霧が立ちこめて、森の中はギルティタウンより薄暗い。
「ここはクリムゾンフォレストっつう森だ。
ボスがルール違反した人間をぶちのめし、そいつらの血で育ったのがこの赤い森だ」
イングウェイがボスを思い出しているのか、神妙な顔つきで説明してくれた。
「ボスってそんなに怖いの?早く見てみたい」
「ボスを初対面で直視できたらすげえよ。ボス見てショック死した奴だっているんだぜ」
イングウェイは真顔で言っている。
「僕が子供だからって、脅かしてそんな事言ってるんでしょ。僕はショック死なんかしないよ!」
僕は頬を膨らませた。
「ほんとに怖えんだよ!」
イングウェイが声を荒げて言い張る。
「イングウェイ、 ボスに会った後、
僕を助けて教会に運んでくれたおじいさんの所に連れって欲しいんだ。
僕、寝てばっかりで、ろくにお礼も言わないで出てきちゃったからさ」
「ジューダスんとこにか。人がいいからな、あのジジイ。
困ってる奴見るとほっとけねえんだよ」
「なんでそんなにいい人が、罪人の街にいるんだろう」
僕は首を傾げて言った。
「ジューダスの野郎は、妻と息子夫婦を強盗に殺されて、
神を信じることができなくなっちまったんだと。
そんなジューダスに信仰が足りないだの言って心の持ちようを責めてきた、
同じ宗教の信徒を殺しちまったらしい。
それからあいつの神は、自分だけだそうだ。悪魔寄りの自己崇拝者になっちまったのさ。
ジューダスは人のいい顔して、恐ろしいジジイだぜ」
昨日の優しいおじいさんと、イングウェイが話す内容が一致しないので、僕は目をパチクリさせていた。しばらく歩いていると、遠くの大木に派手な模様の大鳥が止まっているのが見えた。
「ようメタリカ。ボスに会いたいからハロウィンを呼んでくれ」
イングウェイは鳥に話しかけた。
『そっちの子供はなんだ、イングウェイ』
と、と、鳥がしゃべった!
「少しの間だが、街に居候することになったアッサムだ。
その間、こいつがする仕事をボスにもらいに来たのさ」
「よ、よろしくおねがいします!」
僕はうわずった声で 、クールな目をした鳥に叫んだ。
『いいだろう』
メタリカと呼ばれた鳥が、 高い声で歌い始めた。数分と経たないうちに、骨のほうきに乗った魔女が荒っぽい運転で僕たちの前に姿を現したが、彼女は木に激突してイングウェイの失笑を買っていた。
「相変わらず、へたくそな運転しかできねえんだなハロウィン」
「やかまし!修行中やねん!
おんどれこそなんや、悪趣味な頭にキテレツなカッコしおってからに、
そのなけなしのセンスを心から疑うわ!」
ほうきから降りたボーイッシュな魔女が、ぶつけた頭をさすりながら言った。
「このボンズを ボスの屋敷に連れて行ったらええんやな」
ハロウィンが呪文を唱えると、目の前に幽霊屋敷のような洋館がパッと現れた。
「うわぁ、すごい!!」
僕は思わず叫んでしまった。
「ええリアクションやなボンズ。驚かれるとイリュージョンの使いがいあるわ」
「イリュージョン?」
「魔女の一流黒魔術とも言うけどな」
ハロウィンが誇らしげに言った。
「ほとんど失敗するけどな」
イングウェイが付け加える。
「やかましい!おんどれは黙ってここで待っとれや!
ボンズをボスに会わせたら戻ってくるさかい」
ハロウィンは憎まれ口を叩くと、僕を引っ張り屋敷の鉄扉を開けた。
◇
「冤罪の一般人風情がでかい口叩きよってからに」
凝ったつくりのバルコニーから続く螺旋階段を登りながら、ハロウィンが呟いた。
「え……冤罪って……?」
僕はびっくりして、ハロウィンに聞き返した。
「冤罪は冤罪や。あの男は何にしとらんで。
地上でトップミュージシャンの売れっ子やっちゅうのに、
なんでこんな街に居座ってんのかウチにはようわからんわ」
「イングウェイは、人殺しじゃなかったんだね……」
僕は少しだけ安堵した。イングウェイはどうして、バンドのメンバーを殺したなんて言ったんだろう。
「ボスは今お昼寝しとる。無理矢理起こすと、ウチ殺されてしまうんよ。
あと30分もすれば起きると思うねんけど、それまで暇つぶしせえへん?」
ハロウィンは僕の手を引き、ライム色の奇妙な部屋に入った。 形容しがたい形の雑貨類が並んでいる。
「ウチの事務所や。街の連中の素性や前科を調べて、管理しとるんよ。
住人の諸々を収めたファイル、 ボンズに特別に見せたるわ。
なんや、あのバカ男の事が気になっとるみたいやしな」
ハロウィンはイタズラっぽく笑うと、ドクロのステッカーが貼られたバインダーを差し出す。僕はそれを受け取ると、イングウェイのページを捜し、見つけた。 ハロウィンの字で、判決・殺人による死刑(冤罪)と書いてある。
「イングウェイが無実だってほんとなの?
メンバーを殺した理由は結局分からずじまいで、不気味な事件だったんだ。
僕はイングウェイが好きだから、ほんとのことが知りたいよ」
半透明の丸いグラスに蛍光色の飲料を注ぎ、僕に手渡そうとするハロウィンに尋ねた。
「喋りたくなさそうやったから、ウチが勝手に調べたんやけどな。
イングウェイは、メンバーの紅一点レベッカとできとったらしいで。
けどメンバーの双子、アーク兄弟もレベッカが好きやったらしいくてな。
そんで……ん―――、見た方が早いわな」
ハロウィンはマーブル模様の棚から、小さなビデオテープを取り出す。
奇妙なアンテナ付のモニターにテープを差し込み、再生を始めた。
◇
そこには『HELL/HOUND』のスタジオらしき場所でベースの練習をするレベッカの姿が映っていた。 時折カメラに向かって、イタズラっぽく、メタリウムサインを見せたりしている。 数分後、スタジオの入り口から、アーク兄弟がギターを持って入ってきた。三人で音合わせかと思いワクワクしていたら、アーク兄弟が無言でレベッカを押さえつけ、強姦し始めた。 僕は絶句し、画面から目を逸らした。
レベッカの悲鳴が、ビデオから痛いくらいに響いている。防音処理の施された室内。気づいて助けに来る人間はおらず、酷い映像がそのまま流れていた。アーク兄は『このビデオを流されたくなかったら、イングウェイと別れて二人と関係を続けろ』と強要している。レベッカは最初から最後まで拒み続けていた。
しばらくして、人が来たらしくスタジオの扉をノックする音がした。扉が開かない事に気づくと、鉄の扉はさらに激しく叩かれる。その叩き方が次第に、バスドラムのように乱暴なっていった。やがてドアが鍵ごと壊れ、スタジオの扉が開いた。
『いかん、この扉は壊れてる。俺が壊したんじゃねえぞ』
ドラムのハイドリヒが、ドアの向こうでぼやいている声が聞こえた。巨漢のハイドリヒが、もげたドアノブを片手に持ち、スタジオにのっそり入ってきた。
『オメーがドラムのノリでぶっ叩くからだろ。どうすんだよそれ』
イングウェイがそれを見て笑いながら、ハイドリヒに続いて室内に入った。スタジオの様子を見るなり、イングウェイとハイドリヒの表情が凍り付いた。最年長のハイドリヒが、目の前の惨事を見るなり怒声を上げた。アーク兄弟をレベッカから引き離そうとしている。レベッカは、イングウェイに『見ないで!』と必死に叫んでいた。イングウェイは愕然としつつも、ハイドリヒと共にアーク兄弟を止めにかかった。
アーク兄とハイドリヒは揉み合っていた。ハイドリヒは手元にあったギターで、思い切りアーク兄の頭を殴る。 打ち所が悪かったのか、アーク兄は起きない。 イングウェイに殴られ床に転がっていたアーク弟が、ハイドリヒに向かって『人殺し!』と叫ぶ。 兄の死に逆上したアーク弟と、ハイドリヒの取っ組み合いになってしまった。
イングウェイは、レベッカを抱き起こして必死に慰めていた。レベッカは『ごめんなさい』と何度も呟くと 、近くにあったペーパーナイフをのど笛に突き刺し、自殺してしまった。白い内装の殺風景なスタジオが、レベッカの返り血で赤く染まる。
アーク弟が、レベッカが自殺したのを見るなり、気でも触れたのか下品な声で笑い出した。 レベッカの傍までふらふらと歩み寄ると、彼女の首に刺さったペーパーナイフを引き抜く。 それを、背後にいたハイドリヒに向かって突き立てた。ナイフはハイドリヒの頬に刺さり、顔面から血が噴き出ている。 ハイドリヒの巨体が倒れ、アーク弟がハイドリヒに馬乗りになった。顔から首にかけて、アーク弟はペーパーナイフでハイドリヒの顔面をメッタ刺しにしている。
イングウェイはレベッカの死体に顔を突っ伏し、泣いているようだった。ハイドリヒが動かなくなると、アーク弟がイングウェイの背中に向かって、ペーパーナイフを突き立てた。 イングウェイは避けもせず、ただ刺されていた。
『お前のせいだ!なんとか言えよリーダー!』
わめくアーク弟を、イングウェイは生気のない顔で見ていた。
『死んだら地獄でバンドやろうぜ』
それを聞いたアーク弟が、また笑い出す。途中で泣き声も混じり、わけのわからない事を言っていた。アーク弟は自分のこめかみに ペーパーナイフを貫通する程突き立て、自殺した。血にまみれたスタジオの中で、 イングウェイだけが残された。イングウェイはつけっぱなしのビデオカメラに気づいたのか、正面に向かって歩き出し 、手を伸ばす。そこでノイズが入り、映像は終わった。
◇
「……」
僕は衝撃的すぎて、口がきけなくなった。
「これな、表の世界に残しておけんゆうて、イングウェイがウチに渡してきたもんや。
例のスタジオでの練習の最中、プロモーションビデオに使う、
普段の練習風景を取ろうとして撮影したらしいで。
この中に、あの殺人事件の記録がバッチリ残っとるんや。
ビデオがあれば、自分の無実を証明出来たはずなのに
あいつはそれをしないで、全員自分が殺したと言いおったんよ」
ハロウィンが、ビデオテープを取り出しながら、理解できないといった風に首を振った。
「イングウェイは、人を殺した仲間をかばいたかったのかな。」
僕はポツリと呟いた。
「自分の女、強姦した男共、かばうかいな普通!?
ドラムのおっさんは、バカ兄弟止めようとした結果一人殺してもうたけど、
どのみち自分以外、全員死んどるんやで。
これ見せて、本当のこと言ったらええと思うねんけど」
ハロウィンが吐き捨てるように言った。
「……なんで、僕にこれを見せたの?」
僕はハロウィンにそう一言だけ言って、口ごもってしまった。
「リッチがここに連れてくる連中は、犯罪なんかに手ェ出しそうもない、
なんや自信のなさそうな人間ばっかでな。ボンズもそんな目ェしとるわ。
それが、あいつの事聞いた途端に目の色変えおったから、
ボンズにとっちゃ、あの音楽バカは特別な存在じゃないかと思ったんよ。
だったら、正しい情報を知っておいた方がええやん。
特別な人間を誤解したまま、もう二度と来れんようなこんな街で、
仕事だけして出てくのは嫌やろ?
湿っぽい話はこの辺にして、そろそろボスに会いに行くでボンズ。
もういい加減、起きとるやろ」
ハロウィンは淡々とそう言うと、僕を連れて部屋を出て、 ボスのいる部屋に続く螺旋階段へ案内してくれた。
「最上階にボスはいるねんけど、初対面ではちょっとキツイかもな 」
ハロウィンが呟くように言った。
◇
「ボス、新入りです。仕事貰いにきたゆうてますわ」
最上階には、ネオンが一面にちりばめられた扉があり、『起きてます』という文字が浮かび上がっている。
『入れ』
低くて、空気が震えそうな声が、部屋の中から響いた。
「しッ失礼します!」
緊張のあまり、僕は裏返った声を必死に絞り出して叫んだ。
ハロウィンが扉を開ける。僕はそこにいるボスを見る。
「うわあぁぁぁぁぁぁあぁぁぁあぁぁぁぁぁ!!!!!」
イングウェイが言っていた意味が分かった。
◇
僕はその場で気絶してしまった。目が覚めると僕の体はイスに縛られ、ボスの目の前に置かれている。
「会話が終わる前に逃げられたら困るんよ」
ハロウィンが僕の隣に立って言った。
『ボーズ、オレが怖いか』
目の前のボスが言った。
「こ、こ、怖いです!」
ボスの五つの顔がニヤッと笑った。
『それでいい。オレにとって、恐れられることは、最高の賛美だ』
今度は五色の笑い声でボスが笑う。僕は逃げ出したかった。目の前にいるボスには、首が五つあった。どれもつぎはぎのゾンビのような顔で、この世の全ての恐ろしさを凝縮したような、もの凄い表情をしている。 巨大な体には足や腕が人間の五倍くらい付いていた。多すぎて、数える気にもならない。その異常に多い腕で、ボスは書類に判を押したり、電卓でなにやら計算していたり仕事をしている。多すぎる足は、光速で貧乏揺すりをし、 あまりの激しさに部屋が小刻みに揺れている。五つある首の二つは、仕事の方に集中し、残りの三つの首が、僕に視線を向けている。こんな人間、想像したこともない。今まで絵本の中で見てきた、どんなモンスターよりも 不気味で恐ろしい。きっと地獄にだって、こんな化け物はいない。
『ボースは、この街で何がしたい』
真ん中の首が僕に聞いた。
「あ、あ、僕は画家になりたいです!!」
僕はもう、半べそをかきながら、裏返る声で必死に言った。
『じゃあ、今日からお前は画家だ。
仕事をさぼったらお前の首も、ここに加わる事になるからな』
左右の六本の腕を上げ、五つの頭部を指さしながら、ボスが言った。
「ボスは腕っ節も強烈やから覚悟しとき」
ハロウィンが笑顔で言う。
「あ、あの、ボスの名前は、な、なんていうんですか?」
僕は震える声で必死に言った。
『右からガンマ、ローディー、カンニバル、メガデス、スレイヤーだ。覚えておけボーズ』
五つの首が一斉に笑った。僕はもう倒れそうだった。
「はっはいッ!
ガンマさん、コーディーさん、カンニバルさん、メガデスさん、スレイヤーさん!」
僕は目を白黒させて言った。自分のとっさの記憶力にビックリした。
『ボーズ』
ボスの右から二つ目の首が、僕にドスの利いた声を掛けてきた。
「はっはいいぃい!!」
僕はまた失神しそうだった。
『オレは、コーディーじゃなく、ローディーだ』
ローディーさんが僕に向かって、不気味な顔でウインクした。僕は泣きながら笑った。
「ボス、もうこのボンズ限界みたいやから、帰すで」
『おう、また来いよボーズ』
ボスが全ての首をこっちに向けて言った。
「はっはっはい!!」
僕は勢いよくイスから立ち上がり、後ろの扉までおぼつかない足で歩いた。
「し、しっ失礼しました!」
僕は入り口で頭を下げてボスの部屋から出る。ドアを閉めると気が抜けて、その場にへなへなとへたり込んでしまった。僕の様子を見て、ハロウィンが笑っている。
「ナイスな失神ぶりだったでボンズ。ボスも喜んどったわ」
ハロウィンが愉快そうに僕の肩を叩いた。
「は、ハロウィンはボスのこと怖くないの!?」
僕は、ボス相手にタメ口で話すハロウィンに向かって、恐れも含めた眼差しで聞いた。
「ウチはボスと住民の仲介役やからな。慣れてもうたわ」
「ボスはモンスターなの?あんな人間見た事ないよ」
「この街の歴代ボスの集合体や。
正確には真ん中の首が、五代目ボスのカンニバルさんやで」
螺旋階段を降りながら、ハロウィンが言った。
◇
屋敷の外に出ると、イングウェイが腕組みしながら、仁王立ちで待っていた。
「遅せえよバカ!一時間近く待ってたぞオレは!!」
イングウェイが怒り出した。
「一時間くらいでガタガタ言うなや!」
ハロウィンも負けじと怒鳴る。
「ボスに用がある時は、また受付のメタリカに声掛けるとええわ。
そんじゃ、また来いやボンズ。ほな!」
ハロウィンはそう言うと屋敷と一緒に、霧のように姿を消した。夢を見てるみたいだ。
「イングウェイ、ボスすごかったよ 。僕、気絶しちゃった」
僕は帰り道、興奮しながら、イングウェイに話した。
「だろ。ボスはもう人間じゃねえよ」
イングウェイが笑いながら言った。
「僕、仕事頑張るよ」
僕はそう言ってこれからの生活を頭で思い浮かべながら、クリムゾンフォレストをイングウェイと歩いた。